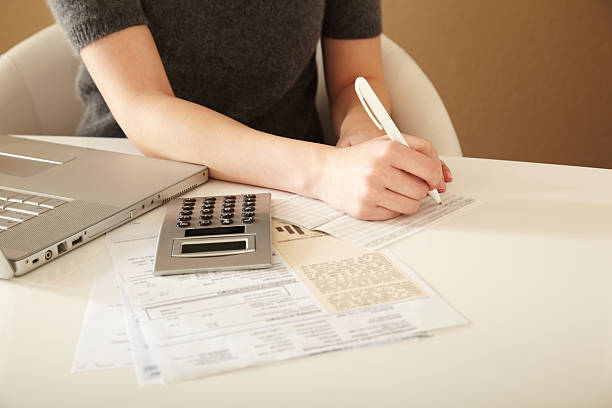看護師の給与とキャリア展望:高待遇で働ける職場の選び方
看護師の給与構造と高待遇の背景 看護師の給与は「基本給+手当」で構成され、特に訪問看護分野では歩合制やオンコール手当が収入を押し上げます。例えば、東京都内の訪問看護ステーションでは、基本給19万円に固定残業代12万円を加えた月額31万円(年収372万円)が基準となり、訪問件数に応じて月10~15万円の追加手当が支給されるケースがあります。これにより、年間500~600万円の収入が可能です。 高待遇の背景には、以下の3つの要因があります。 高収入が期待できる職場タイプ 未経験者がキャリアをスタートする方法 未経験者を受け入れる施設では、以下のサポート体制が整備されています。 給与交渉と長期キャリア形成のポイント 今後の展望と行動計画 2025年度からは、AIを活用した遠隔看護モニタリングが保険適用され、テクノロジーを駆使した新しい看護形態が登場します。これに伴い、ITスキルを持つ看護師の需要がさらに高まると予測されます。