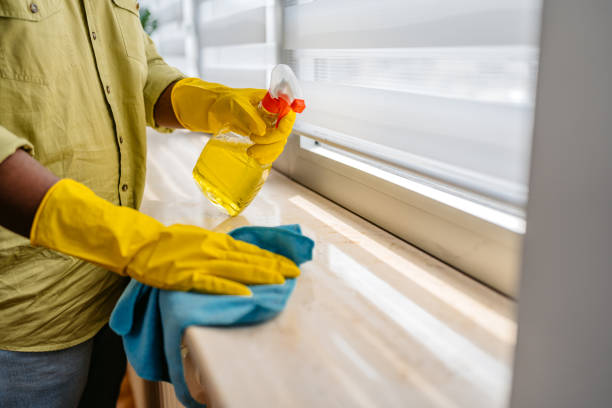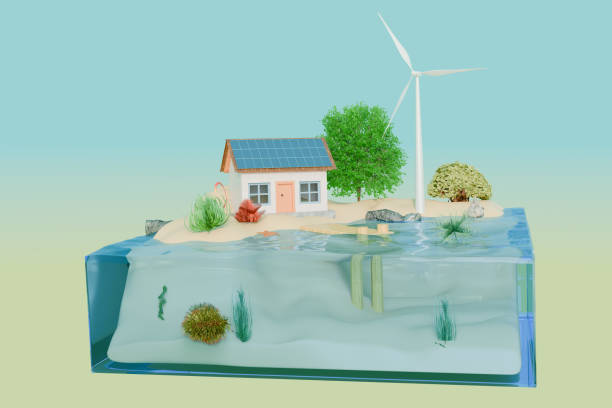お雛様処分:伝統を尊重した適切な方法
お雛様を処分する主な方法 お雛様を処分する方法はいくつかありますが、最も伝統的なのは「神社やお寺で供養してもらう」方法です。全国には雛人形の供養を行っている神社仏閣が数多くあり、毎年決まった時期に供養祭を実施しています。下表は主な処分方法とその特徴です: 処分方法 費用相場 必要な手続き 特徴 神社仏閣での供養 3,000-10,000円 事前予約が必要な場合あり 伝統的な方法で心置きなく処分できる 自治体の粗大ゴミ 500-3,000円 自治体に申請が必要 手軽だが供養の儀式はない 専門業者による回収 5,000-20,000円 業者に連絡して回収依頼 自宅まで引き取りに来てくれる リサイクルショップ 無料~買取 状態が良いものに限る まだ使える雛人形を次の家庭へ 状態が良いお雛様であれば、リサイクルショップやフリマアプリで譲る方法もあります。特に高級な京雛や御所人形は、コレクターから需要がある場合も少なくありません。ただし、人形に傷や汚れがある場合は、供養や廃棄を検討した方が良いでしょう。自治体の粗大ゴミとして処分する場合は、事前に申請が必要で、指定された日時に指定場所まで運ぶ必要があります。 神社仏閣での供養の流れ 神社やお寺でお雛様を供養してもらう場合、まずは近隣の神社仏閣に問い合わせてみましょう。多くの場合、毎年ひな祭りの前後に供養祭を実施しており、事前予約が必要な場合もあります。供養料は3,000円から10,000円程度が相場で、神社によってはお札やお守りを授与してくれるところもあります。 供養の方法は神社仏閣によって異なりますが、一般的には神職や僧侶がお経をあげ、お焚き上げをします。最近では環境に配慮して、焼却せずに専用の施設で処分する神社も増えています。遠方の有名神社に供養を依頼したい場合は、郵送で受け付けているところもあるので、問い合わせてみると良いでしょう。特に人形供養で有名な神社としては、東京の浅草寺や京都の地主神社などが知られています。 供養祭に参加する場合は、お雛様を風呂敷や布で包み、感謝の気持ちを込めて持参します。供養の際には、これまで守ってくれたことへの感謝の気持ちを伝えると良いでしょう。供養後は、神社からお焚き上げの証明書を受け取れる場合もあります。 自治体の粗大ゴミとして処分する場合の注意点 お雛様を自治体の粗大ゴミとして処分する場合は、まず居住地の自治体のルールを確認しましょう。多くの自治体では、事前の申請と処理券の購入が必要です。申請方法は自治体によって異なり、電話やインターネットから可能なところもあります。粗大ゴミの収集日は限られているため、計画的に手配する必要があります。 お雛様をゴミとして出す際の包装方法にも注意が必要です。人形や飾りがばらばらにならないように、しっかりとまとめてから段ボール箱やゴミ袋に入れましょう。特に刀や笏などの細かい部品は、なくならないように注意が必要です。自治体によっては、大型の雛段をそのまま出すことができない場合もあるので、事前にサイズ制限を確認しておきましょう。